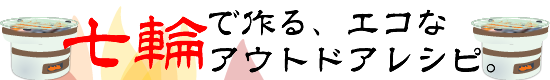一九九九年、春。
ツッチー達が暮らす磯子の寮にほど近い公園で花見が開催された。幹の太い立派な桜が大きく枝を広げているその公園は、徒歩七~八分という好立地なので、寮長の了解を得て豚汁やおでんを寮の調理場で準備した。
重い寸胴にたっぷり湯を沸かし、キロ単位で購入した豚バラ肉と刻んだ大根、にんじん、長ネギを加える。湯が沸いたら出汁入りの味噌をこれまた山ほど入れる。そうして出来上がった豚汁を台車に載せて、数人の男手で講演に運び込んだ。ところが豚汁でいっぱいの、寸胴のあまりの重さに腕は痺れる、汁はこぼれる…のてんやわんや。屋外で、大人数の宴会向きの調理方法はないものかと途方に暮れたのがそもそもの始まりだった。
この年の潮干狩りと花見が終わってしばらくすると、ツッチーと藤井君から連絡があり、ダッチオーブンなるものを買ったから遊びに来いという。原付で向かった磯子の寮の庭には、ダッチオーブン二台が並んでいた。

真新しいダッチオーブンはまだ鉛色。蓋にはLODGE(ロッジ)と浮き彫りの文字がある。当時はまだ選べるほどの関連本は無かったが、完成写真付きのレシピ本と簡単な歴史が書いてあるウンチク本一冊ずつを藤井君が揃えていた。
「ダッチオーブンはカウボーイたちの料理には欠かせなかった。ダッチオーブンに肉の塊り、豆を入れる。穴を掘ってよく熾きた炭を穴底に敷き、ダッチオーブンを埋める。そのうえからまた焚き火を被せてカウボーイは牛追いに向かう。夕方掘り出されたダッチオーブンは見事に肉と豆を柔らかく煮込んでいた。」
おお!藤井君の読み上げた、その男らしい料理法に感嘆の声が上がった。
「使うほどに、磨くほどに、ダッチオーブンは黒くなる。使い終わったら湯を沸かして汚れを落とす。また焚き火にかけてよく乾燥させる。油を薄く塗り、布でしっかりと磨き上げる。使い込まれた黒光りのするダッチオーブンはブラックポットと呼ばれ、代々、子供へと受け継がれていくのだ。」

おおう!藤井君が続けたその頑健な調理器具の説明に、まだ嫁の当てもない男たちが、未来の息子たちにダッチオーブンを託す瞬間を瞼の裏に思い描いた。藤井君は丸い眼鏡をずりあげながら、さらに続けた。
「『慣らし』を終えたばかりのダッチオーブンには、油のよく馴染む調理が良いと。またニンニクなどの香味野菜を使うと鉄臭さが消える」
おおう……。鉄臭さが消えるのか。なるほど、なるほどと、初めての調理器具とその説明に、なすがままの我々は素直に従うことにした。安くて旨い鶏肉は日頃のバーベキューでも使い慣れた食材なので安心感もある。