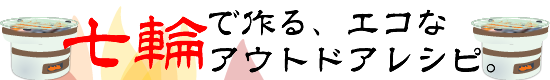ちょうど昼近くに到着したので腹が減っている。酒もすっかり抜けて胃袋が活発になり、ぐるぐると音を立てている。メシ、メシと言いながらマスクをしてシュノーケルをくわえ、フィンを履いてすぐに海へ引き返した。

透明度は10メートルほど。ちょっと沖まで泳ぎ出ただけで、水底で魚が泳ぎ回っているのがよく見える。「カニや貝などを適当に探してきて」と東さんに言われたものの、まったく見つけられない。とりあえず東さんにくっつくように泳いでいると、東さんが大きなゴロタ石の隙間をじっと見つめ始めた。
大きく呼吸をしながら手銛を捻ると伸縮式の柄が伸びて2メートルほどになった。柄尻のゴムに手を掛けて、銛の中央あたりまで引きあげる。東さんが目一杯吸ってから息を止めて潜り水底付近に辿り着く。幹の太い海藻、カジメにつかまる。そのままぴたりと海底に身体を張りつけ、動きを止めた。
どしゅっ。
と音が聞こえたように思った。
ゴムを放った手銛は数10センチ先でなにかに刺さっているようだ。ゴロタ石の隙間からもうもうと須永舞い上がる。舞い上がる砂煙から引き出した銛先には、青く分厚いブダイが突き刺さっていた。そして東さんは悠々とフィンを蹴りつつ浮上して、腰に巻き付けていた網を獲物に被せたのだった。
すげぇ!本当に魚を獲った!
マスク越しにツッチーが唸っている。オレも興奮のあまり声にならない歓喜と驚きがシュノーケルから漏れていたようだ。

浜にあがった東さんは、びったんびったん暴れるブダイの頭をあまり切れないダイビングナイフでごりごりと切り落とした。小枝と、浜に打ち上げられ乾燥している海藻を集めて着火マンで火を点ける。真っ白な煙をもくもく上げていた焚き火が徐々に大きくなる。ゴロタ浜にはいくらでも流木が転がっているから、どんどん焚き火にくべて充分な火力を準備した。

ぶしゅっ!保冷剤できりっと冷えた缶ビールを開け、興奮冷めやらぬまま乾杯。泳いで冷えた身体も太陽熱で熱くなった椅子替わりのゴロタ岩と焚き火で十分に温まっているし、太陽は無人島にいる我々のためにだけ照っているから、ビールが最高にうまいのだ。

ブダイの鱗は親指の爪よりもでかいので、ダイビングナイフの背でごすりながら剥がす。すでに空いた缶ビールの缶の上部は切り取って、海水と真水を半分ずつ入れて、エリちゃんが拾ってきたシッタカという小さな巻貝を入れる。そして焚き火の横にビール缶を置くと、すぐにぐつぐつと湯が沸き始めた。
まずはブダイの刺身。切るというよりは削り取るようにして剥がした身を手で醤油に漬けてつまむ。うん、旨くない。獲りたての魚は刺身よりも焼いたほうがうまくなるようだ。


一口大に切ってから焼くつもりだったが、相変わらず切れないナイフで身を剥がすのが面倒になった東さんは、どさりと焚き火の上の焼き網にブダイを載せた。川がちりりと反り返り、身はどんどん真っ白になっていく。ペットボトルの醤油をかけまわす。ブダイから醤油が焚き火に落ちると、じゅわっという音とともに香ばしい匂いが辺りに広がる。これは屋台のとうもろこし屋の匂いだ。さあ出来た。焼き網ごと火から外して割り箸でブダイの身を突っつく。